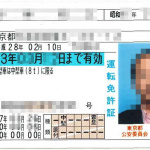目次
■ペダル付きの原付もある!

18歳から取得できる普通自動車免許に対し、16歳で取得できるのが2輪免許。なかでも実技試験がない原動機付自転車免許、通称:原付免許はお手軽ですよね。
普通自動車免許を取得してももれなく付いてくる原付免許ですが、その2年が待てずに「原付免許をまずとって、18歳になったら4輪免許!」、そんな流れで免許取得を計画している少年・少女たちも多いことでしょう。
その「原付」バイクと免許などについてざっくりと調べてみました。
●原動機付自転車とは?

道路交通法で総排気量が50cc以下、電動機は定格出力0.6kW以下の2輪車のこと(法規上の条件を満たした3輪、20ccを超え50cc以下の[または0.25kWを超え0.6kW以下のもの]3輪以上のものも含む)を、原動機付自転車といいます。原付(ゲンツキ)とか原チャリともいいますね。
ちなみに、同じ原付でも「原付2種(道路運送車両法/51cc~125cc以下、電動機は定格出力1.0kW以下)」っていうのがあるのですが、これに乗るには「小型限定普通二輪免許」が必要になるので、今回はこの原付2種は除き、原付1種だけに限って進めます。

原付にはギヤチェンジするタイプと(クルマでいうところのMT)、アクセルとブレーキ操作だけのスクータータイプ(AT)の2種類があります。が、自動車とは違い、原付に限ってはひとつの免許でどっちのタイプも運転することが可能です。
「原付って?」を調べていくうちに、意外と知らないことがあるのが分かりました。「ペダル付きの原動機付自転車」の扱いについてです。要は原付に自転車のペダルがついていて、足漕ぎでも動くし原動機でも動くという「なんとなく中間的な扱い」をされていた自転車+α(原付-αか?)みたいなヤツのことです。しかし、これも「原付」の仲間で、当然、足漕ぎだけで動かそうが原付免許が必要なのです。歴史的にみるとこちらが原付の元祖なんですよね。
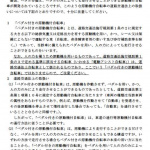
幼稚園の送り迎えをしたりするママチャリでよくある「電動アシスト付き自転車」と似ているのですが、原動機の出力が大きいので立派な原付。「コレは原付1種だ!」と、わざわざ警視庁交通局が御触れを出しているだけあり、自転車感覚の勘違い無免許者が多かったのだと推測。要注意です!
ただし、2023年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等を原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」に区分する改正道交法が適用されることに。以下の条件を満たせば、16歳以上なら免許不要で乗ることが可能です。
・車体の大きさは長さ190cm以下、幅60cm以下
・原動機として定格出力が0.6kW以下の電動機を用いる
・時速20kmを超える速度を出すことができない
・走行中に最高速度の設定を変更できない
・AT機構を採用している
・最高速度表示灯を備えていること など
上記にくわえて、
・道路運送車両法上の保安基準に適合している
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしている
・標識(ナンバープレート)を取り付けている
ことも必要です。もちろん、乗車用ヘルメットの装着も推奨されています。
【2輪車の免許の種類って?】

2輪車(バイク)の免許には、今回紹介する「原付免許」の他、「小型限定普通二輪免許」「AT小型限定普通二輪免許」「普通二輪免許」「AT限定普通二輪免許」「大型二輪免許」「AT限定大型二輪免許」があります。この中で一番手軽で安く取得できるのが、原付免許ということですね。
昔は400ccまで乗れる免許を「中型(中免)」って呼んでましたが、1996年の改正から「普通二輪免許」という呼称になりました。そのほか「AT限定○○」などが増えたりして、現在は7種類に区分されています。
【原付免許は最短1日で取得が可能】

原付免許は、教習所に行かなくても取得できるお手軽なもの。各都道府県の運転免許センターか試験場で行なう「適性試験」と「学科試験」に合格後、3時間の「実技講習」と「ビデオ講習」を受けるだけなので、頑張れば最短一日で原付免許証がもらえます。トータル約6時間前後ってところでしょうか。
(※「実技講習」は、ところにより「原付講習」や「技能講習」とか言いますが、ここでは「実技講習」とします。)
■必要書類はけっこうある!
原付免許取得時に必要な申請書類等は、以下の通り。取得がお手軽な割にはけっこうな量が必要です。
[書類等]
・住民票(本籍地の記載があり、発行後6ヵ月以内のものでコピーは不可)
・健康保険証/パスポート/マイナンバーカードなど、公共機関で発行された本人確認ができる証明書
・顔写真(6ヵ月以内に撮影されたもの。縦30mm×横24mm)
・筆記用具(HB以上の鉛筆やボールペン、消しゴムなど)
・印鑑(認め印でもOK)
・視力矯正が必要な人はメガネやコンタクトレンズ
・試験場にある運転免許申請書/受験票
(※国籍が日本でない方などはそのほかいろいろな書類が必要になります)
[費用]
・受験料=1500円/交付手数料=2050円/講習受講料=4500円(※法令で定められる標準額)
■まずは視力・聴力等の適性試験。
この「適性試験」に受からなくては、いくら学科試験に自信があっても免許取得はできません。
[視力]
・両眼で0.5以上。
・片眼が見えない場合、もう一方の眼の視力0.5以上+視野左右150度以上。
[色彩識別能力]
・赤・青・黄の識別ができる。要は信号機の色が分からないと免許は取れないのです。
[運動能力]
・運転に支障を及ぼす身体障害がない。日常の生活に問題がなければOK。
■学科試験は30分/48問、90%正解で合格!


では、実際の取得の流れをみていきましょう。
まずは試験場で受付したあと、書類に記入し、受験料を支払い、適性試験を受けた後に学科試験を受けます。
学科試験は回答時間は30分。文章問題が46問(1点)、危険予知のイラスト問題が2問(2点)の計48問で、50点満点中45点以上が合格です。
ではここで、学科の文章問題例を見てみましょう。ここにあるのは、いわゆる「ひっかけ問題」(正解は全部「×」)、こんなものがあります。
Q. マフラーを改造していない原動機付自転車なら、著しく他人の迷惑になるような空ぶかしは禁止されていない。
A. 「×」 マフラーの改造をしようがしまいが、他人の迷惑になる騒音を出してはいけない。
Q. チェーンの張り具合は、車に乗った状態で点検する。
A. 「×」 チェーンの張り具合の点検は、降りた状態でスタンドをはずし、前後の車輪が地面に接地した状態で行なう。
Q. (1種)原動機付自転車に同乗する人も、つとめてヘルメットをかぶらなければならない。
A. 「×」 そもそも(1種)原動機付自転車は二人乗り禁止。
Q. (1種)原動機付自転車でリヤカーを牽引するときの最高速度は、時速20km/hである。
A. 「×」 牽引するときの最高速度は、時速25km/h。
m? 秒? km/h?等、な~んかイヤラシイ、ちょっとした違いの問題などがあるので、予習をして臨んだ方がいいですね。
■実技講習ではこんなことをします!
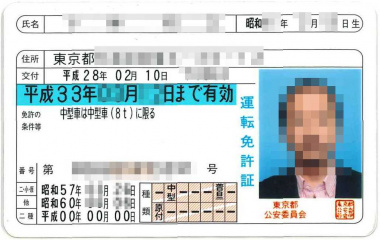
ここまでくれば、あとは「実技講習」3時間と「ビデオ講習」さえ受ければ、原付免許証取得!となります。
実技講習では、原付に乗る際の注意事項、基本操作、基本走行、応用走行、安全運転の知識等を順を追って学びます。
・ヘルメットの着用方法では、正しいあごひものしめ方。
・肩や肘に力の入らない正しい運転姿勢。
・スムーズなアクセルの回し方とブレーキ操作。
・8の字、カーブ、徐行の仕方。
・スムーズな進路変更と安全確認。
・正しい右・左折の仕方と安全確認。
・渋滞の中での優先順位。
等、様々な安全運転・法規厳守のことなどを実技練習と共に学びます。
手軽に免許が取れ、車体も安く、小回りが利いて、通勤、通学、買い物等、使い勝手のいい原付。が、原付ならではの交通ルール(違反、やぶると罰金・免停も!)もたくさんあるので、原付は手軽で気軽!だけど、それだけとは思わずに、しっかりとルールを守って乗りましょう!
※2021年8月の記事を2023年7月12日に追記・再編集しました。
(永光 やすの)
PHOTO協力:Motor-Fan.jp
【関連記事】
運転免許証の種類、表記、条件とは?【意外と知らない自動車運転免許証・まとめ】
https://clicccar.com/2020/02/05/952769/
令和になって増加の危険性あり!? 運転免許証を「うっかり失効」してしまったらどうすればいい?
https://clicccar.com/2020/01/22/949838/
【JAPANキャンピングカーショー2018】コンパクトに折りたたみ可能な100%電動バイク「BLAZE SMART EV」
https://clicccar.com/2018/02/12/558631/